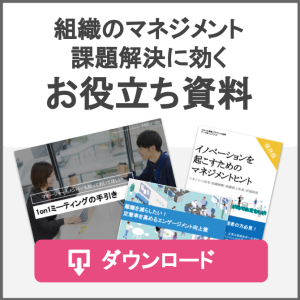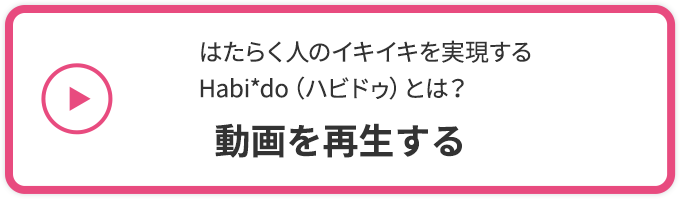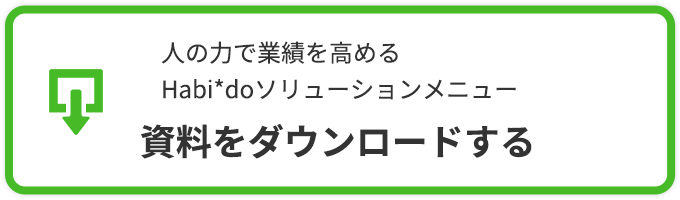経営者の皆さま、「働き方改革」順調に進んでいますか?
ニュースでも取り上げられ、社会的認知も高くなったため、多くの会社で実施が進んでいることと思います。
しかし、経営者が意味を取り違えてしまうと、改革は間違った方向へ進んでしまいます。

たとえば、法整備が抜けているのを逆手にとって年間休日を減らし、有休消化を半強制的に促すといった悪手。社内の規程を変えただけでは済まないかもしれません。
「とりあえず、罰金を取られない程度に年間有休消化日数が消化されればいい…」「ほかの中小企業も、同じようにしているから大丈夫」などと、安易に考えているなら要注意です。
そのような考えは、経営者側の無理やりな理論でしかありません。
働いている社員側の個人的な心情としては、「この会社の経営者はこういう行為を平気でするのだ」思ってしまいますし、結果モチベーションが下がり、企業倫理がないと判断されてしまいます。
果たして、会社の将来にとって、そのような表面的な「改革」は、ベストといえるでしょうか。
働き手不足の解決を目指す「働き方改革」
「働き方改革」とは、政府が主導する、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジでもあります。
この改革がうまくいけば、企業にも社員にも働きやすい社会が実現するでしょう。
しかし、間違った運用をすれば、致命的な傷を負うかもしれません。
ここ数年、社会課題として、人口不足による労働力不足が叫ばれています。

すでに、人材の確保に苦労している企業は多く、特に中小企業の人材不足は深刻です。
しかし昔のように、残っている社員のマンパワーで押し切る方法は、もう通用しません。なぜなら、長時間労働や残業といった働き方は、結果的に生産性を下げ、日本経済にも悪影響をもたらすことが明確になってきているからです。
そこで実施された、生産性向上のための国をあげての取り組みが、いわゆる「働き方改革」です。
しかし、すべての会社がその目的に沿って順調に実施できているかというと、そうではありません。実際、間違った解釈で社員に負担をしいる企業や、無理やり労働時間を短くしたため、業務に支障をきたし、管理職以上の役職持ちに残業が増えている…という「ひずみ」も出始めているのです。
しかし、上司がサービス残業をしているのを見ると、誰も昇進したいと思わなくなります。
これでは社員のモチベーションが保てないどころか、低下する一方ですよね。
日本の長時間労働と、社員の「健康・安全」
他の国に比べて、長時間労働が多いといわれる日本。
そして、労働者の過半数以上は、長時間労働をしている、いわゆる「正社員」です。
近年多くなった非正規雇用者でさえ、9時〜17時のなど、それなりにまとまった拘束時間が労働条件として明示されていることが多く、子育てなどで短時間労働を希望すると、パートやアルバイト待遇の雇用しか見つからないのが現状です。
しかし働き方改革では、長時間労働を減らし、生産性を高めることが求められます。
厚生労働省が定める過労死ラインとは
過労死のニュースが出るたび、長時間労働に対する問題意識が高まっています。

「過労死ライン」というものをご存知でしょうか。
主な基準は2つあり、
- 残業(時間外労働)が、1か月で100時間以上
- もしくは2~6か月にわたって継続して80時間を超えていること
この2つの基準を超えていると、何らかの病気が発症した場合、「業務と発症との関連性が強い」とされ、いわゆる「労災」による給付を受ける基準に達していると判断されます。
「1日6時間以上の睡眠がとれないと、病気リスクが著しく高くなる」という論文・統計によって、最低限の睡眠時間の確保できる労働時間は、この2つの基準以下であるべきという設定になっているのです。
この基準はあくまで「目安」にすぎませんし、ショートスリーパーで6時間も睡眠をとらないといった方もいるでしょう。同じ仕事量であっても、その人の状況や仕事の環境などによって自身の体への影響は変わります。しかし厚生労働省の通達においては、この2つが示されている基準となっています。
政府の「働き方改革」推奨によって、今後、過労死レベルの基準時間が減ることはあっても、増えることはないでしょう。
本人が「大丈夫」と言ったから…仕事が終わっていないから…というのは、会社側の勝手な理論です。まずは国の定め基準を超えない運用をして、個々人への負担の偏りをなくす対応が求められています。
時代は変わったから、売れなくなった…は間違い
バブル期より前から社会人をしている方は、このような社会変化についていけないかもしれません。
しかし、時代は大きく変化しています。
昔は、ただ長時間働いただけで、その時間分に比例して売り上げが上がっていました。
しかし今は、どんなにいい製品であっても、「作っただけ」では売れません。そして、「モノづくり」だけでは売り上げを確保しにくくなり、ビジネスの中心は「コトづくり」へと、時代と環境が変化しています。
「コトづくり」とは、単純な「モノづくり」とは違い、売り方や、どう作ったかというストーリーを含めて、トータルプロデュースをすることを指します。

販売開始から135年がたってもなお売り続けている「三ツ矢サイダー」(アサヒ飲料)を例に考えてみます。
サイダーは透明。保存料や着色料を使用せず、安心安全なこだわった水を使用。品質へのこだわり。
日本生まれ、安心・安全、爽快感を売りにしています。そして、“国民的炭酸飲料”としての信頼を裏切ることなく基本を押さえつつ、飽きられないよう横展開やターゲットをずらすといった取り組みも続けています。
100年以上続く老舗企業である三ツ矢ブランドも、商品を磨き飽きられない工夫を続けています。
その「モノ」がどう作られて、その製法にはどういった価値があるのかなどを、デザイン的な表示や、わかりやすいブランドストーリーと絡め、イメージを喚起させる単語とともにアピール。そこまでの付加価値を示さないと、「モノ」が売れづらくなってきているのです。
その付加価値をうまくユーザーに伝え、まるごと売り方までをプロデュースができれば、「モノ」は売れ、会社の価値も上昇します。
つまり、労働の観点にも、
長時間働くことから生み出される成果 < 短時間でも柔軟な発想から生み出される成果
という変化が起きているのです。
短い時間の労働でも、個人の発想や機転・工夫などを評価し、その才能を活用することで、人材不足や長時間労働を解決できるようになってきました。
多種多様な人材・働き方の導入を認めなくては、先はない
労働力人口が減少する日本社会。
これから、子育てや介護、また身体的物理的な理由で、長時間労働をよしとしない・できない方は増える一方でしょう。
しかし、そのような長時間労働が不可能な人材を、いかにうまく適宜採用し、配置するかは、すべての会社にとっての急務です。
人口統計からみても、長時間労働可能な人材が増えることがないのは、明白だからです。
女性、高齢者、外国人などを登用できる規程を早急に整備し、短時間労働でも働ける環境の整った企業が躍進していくのは、当然ではないでしょうか。

「雇用の多様性」は、会社にとってメリットとなるはずです。
新しい層の人材登用が新しい視点を生み出し、新規事業やイノベーションをもたらすかもしれませんし、数年前はただの主婦だった、優秀な人が採用され、数年後には社長になっている…という企業が増えるかもしれません。
社会の評価基準が変わります。
ただただ長時間働くだけでは、売り上げも上がらず、評価もされない時代。
逆に言えば、ただ長時間残業している社員が評価される時代は終わり、アイデアとコミュニケーションによって、いかに効率よく働けるかが、社会の評価基準となっていくでしょう。
働き方改革を成功させたいと思うなら、ただ単に残業抑制をするのではなく、
・基本労働時間内で効率よく仕事をこなし、退勤する社員こそ優秀だと評価される仕組みをつくる
・社員が、働くモチベーションを上げていける仕組みをつくる
という、この2点が重要ではないでしょうか。
最近は、シェアワークといった新しい雇用形態を導入する企業も増えはじめています。労働時間が短くても、会社に貢献してくれる社員には、かわりありません。
一人ひとりの評価を、労働時間の長短ではなく、内容でしっかりと評価しましょう。
まとめ:従業員一人ひとりに「働き方改革」が浸透するまでには
法律で規制があろうとも、いくら取り組みを続けようとも、社内に意識を根付かせるには、一筋縄でいかないかもしれません。今日明日で、いきなり全社員の意識を取り換えることはできないからです。

また最初は、「時短勤務なのに、あの人の方が評価がいいの?」という批判も出るでしょう。
しかしそれも、正しく個人を評価していれば、説明できますよね。社員とコミュニケーションをとって、自身を鑑みてもらえれば、なにが足りなくてその評価になったのかは、理解されます。
改革は、経営者からの一方的な通達では実現しません。
徐々に、風潮を改めましょう。
経営者が自ら旗を振り、会社をこうしたいと発信し、取り組みを続けることで、徐々に社内浸透を進めましょう。その結果、改革後の風土が当たり前になれば、マインドチェンジは成功です。
社員側も、企業に対して主張できる権利の幅が広がり、より自由に働ける可能性を広げられます。
本当の意味での「働き方改革」は、社員自らが自分を振り返りながら、自らの「働き方」を変革させていくものだからです。
目指すべき「働き方改革」のゴールは、社員一人ひとりが、限られた時間や期限の中で仕事をやり切り、成果を出すために自発的に動けるようになること。
そして、それができる環境を整えられるのは、経営者と管理職です。
働き方改革の成功は、あなた方が握っているのです。